2025年07月24日
「業績が厳しいから、従業員の給料を下げたい」――そんな悩みを抱える中小企業の経営者や幹部の方は少なくありません。とくにコロナ禍や急激な社会変化のなかで、賃金水準の見直しを迫られた企業も多いでしょう。しかし、労働者の賃金は、単に「同意をもらえばOK」「就業規則を変えれば済む」といった単純なものではありません。形式的な同意や手続きを踏んでも、後になって裁判で“無効”と判断されるリスクがあるのです。
この記事では、労働契約法や裁判例をもとに、「賃金引下げが許される条件」「就業規則変更の注意点」「コロナ禍における対応の特殊性」について、企業法務に強い弁護士の視点から解説します。賃金を下げる前に、法的な落とし穴を避けるためのポイントを押さえておきましょう。
賃金引下げは自由にできない?就業規則と労働契約の基本ルール

賃金を引き下げるには、まず労働契約法9条に基づく「労働者本人の同意」が必要です。これは賃金が生活に直結する重大な条件であり、使用者の一存で変更することは原則として認められていません。
参考:労働契約法(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。
また、「同意を得ればOK」と考えて個別に同意書を取り交わすケースもありますが、形式的な同意だけでは無効とされることもあるため注意が必要です。たとえば、同意が強要されたと疑われる場合や、同意内容の意味を労働者が十分に理解していなかった場合、後から「無効」とされるリスクがあります。
参考:労働契約法(就業規則違反の労働契約)
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
つまり、賃金引下げを行うには、①労働者の真摯な同意、②就業規則との整合性、③手続の適正さをすべて満たす必要があります。
-
就業規則の不利益変更が認められる条件と、裁判例からの学び
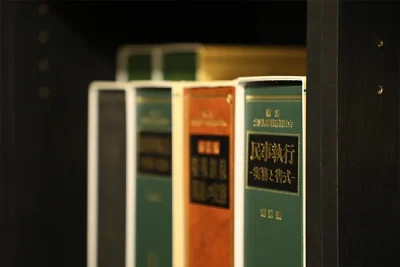
労働者の同意を得られない場合でも、労働契約法10条により「合理的な理由」と適切な手続を満たせば、就業規則の不利益変更は有効になる可能性があります。
参考:労働契約法
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
裁判例を通じて、どのような場合に合理性が認められるのかを見てみましょう。
労働者が退職金規定の変更に同意していたにもかかわらず、最高裁は「説明不足で真に理解しておらず、同意は無効」と判断しました。形式的な合意ではなく、実質的な理解と納得が重要であることが示された事例です。
60歳定年制のもとで55歳以上の従業員の賃金を大幅に減額する就業規則変更を行った事案。年金までの収入が途絶えるという大きな不利益があるにもかかわらず、緩和措置が不十分だったため、就業規則の変更は無効と判断されました。
これらの裁判例が示すように、合理性の判断では以下が問われます。
・不利益の程度と内容
・変更の必要性(経営上の事情等)
・緩和措置や代替策の有無
・説明・周知のプロセス
・労使交渉や社内手続の適正さ
つまり、「就業規則を届け出た」「同意を取った」というだけでは不十分であり、“納得できるプロセス”と“社会通念上の合理性”が揃ってはじめて有効になるのです。
コロナ禍・業績不振時の賃下げはどこまで許されるか?

コロナ禍のような社会的危機は、経営状況の悪化を理由に賃金見直しを考える大きな要因となりました。では、「コロナ不況だから仕方ない」は、賃下げの合理的理由として通用するのでしょうか?
結論としては、一定の合理性は評価されるものの、それだけで正当化されるわけではありません。
裁判所が重視するのは以下のポイントです。
・経営努力(売上改善策の実施)を行っていたか
・他の手段(助成金活用・役員報酬の減額等)を検討したか
・労働者への説明や協議のプロセスが適正だったか
・一部の従業員だけを狙い撃ちしていないか
たとえば、業績不振を理由に全従業員の賃金を一律で10%カットする場合でも、説明や協議を経て、代替策の検討・将来の回復見通しなども共有していれば、合理性が認められる余地はあります。
一方で、「とにかく給与を減らす」という姿勢で一方的に進めた場合は、たとえ社会的危機が背景にあっても、変更無効のリスクが残ります。
まとめ
賃金引下げは、単なる業績不振や従業員の同意だけでは正当化されません。就業規則の変更には、合理性・手続・説明責任が不可欠であり、裁判でも厳しく判断されます。特にコロナ禍のような特殊事情がある場合でも、「会社の努力」や「労働者の納得」を欠いた変更は無効とされるおそれがあります。賃金や就業規則の見直しを検討する際は、早い段階で弁護士に相談し、慎重に進めることが重要です。
【弁護士の一言】
経営者としては、従業員との契約は、対等な契約ではなく、労働法による大きな修正が入った契約になる、ということを知るべきです。すでに何人もの従業員を雇用している経営者は当然のことと思われるかもしれませんが、特にスタートアップ、個人事業主の段階ですと、労働法による強い規制に驚く方も多々いらっしゃいます。今回ご紹介したように、単に「同意」ではだめで、「真摯な同意」が必要というのも要チェックです。何をやったら「真摯な同意」になるんだという点も、抽象的な基準しかないのも問題に感じます。労働法について考えるたびに、経営者側は悩ましい問題を抱えているなと実感いたします。
