2025年07月24日
リフォーム工事を巡るトラブルは、契約書や見積書に記載された「業務範囲」と、顧客が「してもらえる」と思っている内容にズレがあることで生じるケースが少なくありません。特に、アスベスト除去のような専門性と費用負担の大きい工事では、そのズレが深刻なクレームに発展することもあります。
実際に、あるリフォーム業者が水回りの交換工事を請け負った際、顧客は「アスベストも完全に除去してもらえるもの」と誤認していたため、工事後に強い不満を表明。担当者の説明が不十分だったとされ、感情的なやり取りに発展しました。
こうした事態において、顧客対応だけでなく、法的整理や社内での再発防止策まで含めた「企業としての危機対応力」が問われます。本記事では、実際に当事務所が対応した事例をもとに、曖昧な説明が引き金となるトラブルの構造と、企業が取るべき対応について解説します。
クレームか説明不足か?境界線が曖昧なトラブルの実態
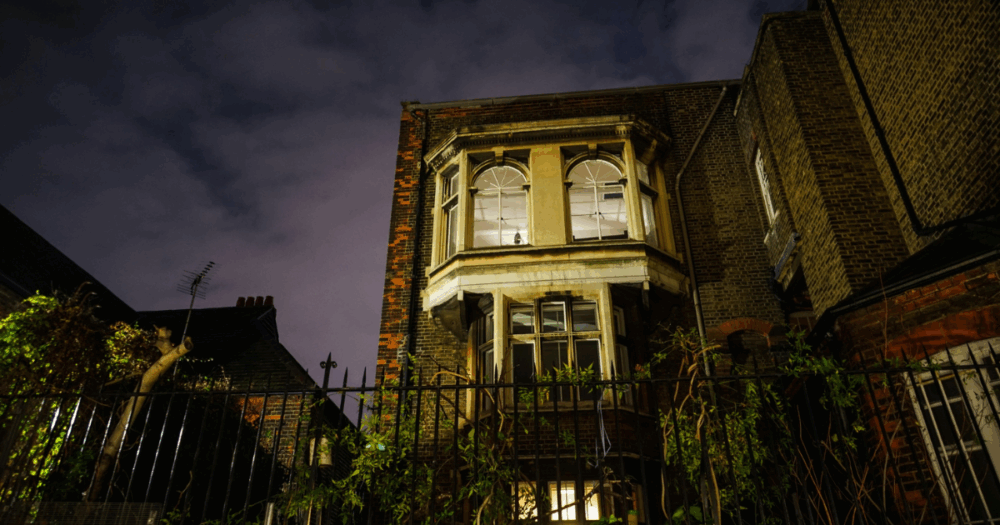
企業にとって、顧客からのクレーム対応は避けて通れない課題です。しかし実際には、「悪質なクレーマーなのか」「説明が不十分だったのか」の判断が難しいグレーなケースが少なくありません。今回の事例もまさにその典型でした。
あるリフォーム業者が請け負ったのは、築古住宅の水回りリフォーム。ところが工事が終わった後、顧客から「(ある業者の言い分によれば)アスベストが残っているじゃないか。完全除去が前提だと思っていた」と強い抗議が寄せられました。
実際には、業者側としては水回りの交換のみを業務範囲と認識しており、見積書にもアスベスト調査や除去といった記載はありませんでした。一方、顧客側は「古い建物であれば当然アスベストも見てもらえると思っていた」「担当者がそういう話をしていた」と主張。両者の認識は大きく食い違っていました。
こうしたトラブルでは、単に「顧客が無理を言っている」と片づけるのではなく、担当者の説明内容、言い回し、補足資料の有無などを総合的に確認する必要があります。
特に、「どこまでが業務範囲か」を曖昧にしたまま見積書や説明が行われている場合、結果として顧客の誤解を招きやすく、企業側の説明責任が問われるリスクがあります。
顧客が強い言葉で不満をぶつけたとしても、背景に「説明がわかりにくかった」「自分の理解と違った」というズレがあれば、それは“クレーム”ではなく“説明不足”として企業側に責任が及ぶ可能性があるのです。
アスベスト除去の法的・技術的な限界と、説明責任のあり方
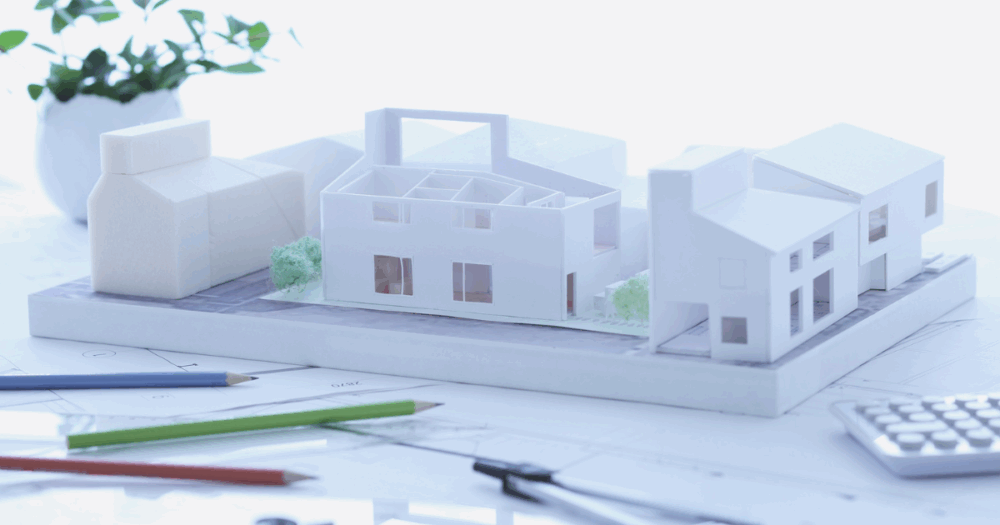
今回の事案のように、「リフォーム工事の範囲にアスベスト除去が含まれているか」が争点となるケースでは、そもそもアスベスト除去という作業が法律上・技術上いかに特殊なものであるかという前提理解が欠かせません。
まず、アスベスト(石綿)除去工事は、労働安全衛生法等の規制を受ける高度な専門工事です。簡単な内装リフォームや水回り工事とは異なり、事前調査・届出・飛散防止措置・専門業者による施工といった厳格なプロセスが求められます。
仮に「完全除去」を行う場合、建材の種類や使用状況にもよりますが、それだけで数十万円から100万円超の追加費用が発生するのが一般的です。
したがって、50万円程度の水回りリフォームに、当然のように「完全除去が含まれている」と期待するのは、技術的・費用的に現実的とは言えません。とはいえ、顧客側はリフォーム業者の説明内容によって、誤った期待を抱くことがあります。
とりわけ築古の建物の場合、「アスベストが含まれている可能性がありますが、今回は調査・除去は対象外です」といった明確な線引きと説明がなければ、顧客は「そこも見てくれるはず」と思い込んでしまうのです。
このようなトラブルを防ぐには、契約前の段階で以下のような工夫が有効です。
・アスベストに関する調査・除去は工事対象に含まれるか否かを明記
・調査自体の実施有無と費用負担について書面で説明
・必要であれば簡易的なリスク説明資料を添付し、顧客の認識を揃える
専門性の高い工事ほど、「やる・やらない」のラインを明示することが、トラブル予防の鍵となります。
弁護士介入での円満解決と、企業が行うべき再発防止策

本件では、顧客と業者の認識のズレが収束せず、感情的な対立にまで発展していました。施主の奥様は「説明が信頼できなかった」と不信感をあらわにし、一方のご主人も一時は強く主張をエスカレートさせる場面もありました。
こうした局面で、弁護士が中立的な立場から介入し、法的視点で「業務範囲の明確性」「契約書・見積書との整合性」「アスベスト除去の法的・技術的制約」などを整理して伝えることで、双方の感情が落ち着きを取り戻しました。
最終的には、顧客側からも「こちらも少し感情的になっていたかもしれない」といった言葉が出るなど、円満に解決へと進めることができました。
これを受けて、業者側では以下のような再発防止策を講じました。
・アスベストが関係する可能性がある工事では、調査・除去の対象外である旨を明示的に伝達
・契約書・見積書での業務範囲の明文化と、文面の標準化
・担当者向けに「顧客説明力」を養う社内研修を実施し、属人的な対応を防止
トラブルが発生する前に、社内体制として「どのような伝え方をすべきか」を整備しておくことは、顧客対応力の向上だけでなく、企業の信頼力を高める重要な投資です。
まとめ
リフォーム業務における説明不足は、たとえ悪意がなくとも深刻なトラブルに発展することがあります。特にアスベストのように法的・技術的に扱いが難しい事項については、契約時点での明確な説明が不可欠です。
今回のように弁護士が介入し、法的視点で状況を整理することで、感情的な対立も冷静な対話へと導くことができます。
もし対応に迷うケースがあれば、早めに専門家へ相談することが、企業の信頼を守る近道です。
【弁護士の一言】
BtoC(=一般顧客、消費者対応)が必要な企業では、業務内容等の説明は非常に大切です。特に、「最初に説明」することが非常に重要なのです。後から伝えても、「そんなの聞いてない!」と不満をぶつけられることも多いです。このあたり、社歴が長くなってくるとトラブルなるポイントや経験値から、業務内容を見通した説明が可能なのですが、社歴が浅い状態の従業員には困難なことも多いです。そのため、企業としては、極力「トラブル事例」を蓄積して、それをマニュアル化して、標準的に従業員が説明できるようにしていく社内体制の構築が重要だと言えるでしょう。
実際に、建設・リフォーム、古美術品買取、Eコマースなど、BtoC企業では社内マニュアルの構築と共に、クレームトラブルは減少しています。このようなお悩みの企業様は、気軽にお問い合わせください。
