2025年07月28日
社内スタッフが書いたイベント告知やブログ記事。広報・情報発信に欠かせないものですが、思わぬトラブルの火種になることがあります。たとえば、「この文章は他社の記事の盗用では?」といった指摘や、「誰が著作権を持っているのか曖昧なまま掲載していた」といったケースです。
特に中小企業では、業務の一環としてスタッフが文章や画像を作成することが多く、社内で著作権の帰属や引用ルールが明確にされていないことも少なくありません。削除済みの記事について問い合わせが来た場合など、対応に困ることもあるでしょう。
この記事では、こうした「スタッフ作成コンテンツに関する著作権トラブル」を未然に防ぐための社内ルール整備のポイントを、企業法務に詳しい弁護士の視点からわかりやすく解説します。適切なルールと教育で、安心して情報発信できる体制を整えましょう。
スタッフが書いた記事や告知文にも「著作権」は発生するのか?

結論からいえば、社内スタッフが作成したブログ記事やイベント告知文にも著作権は発生します。著作権は、創作的な表現をした時点で自動的に発生する権利であり、登録や申請は不要です。つまり、社員が自らの発想で書いた文章やデザインには、たとえ短文であっても「著作物」として保護される可能性があります。
ただし、ここで注意すべきは「その著作権は誰に帰属するのか」という点です。多くの場合、社員やアルバイトが業務として作成したコンテンツは、「職務著作」として会社に権利が帰属します(著作権法15条)。とはいえ、契約書や就業規則で明確にしていない場合、後々「自分の作品を勝手に使われた」と主張されるリスクもあります。
さらに、フリーランスや業務委託スタッフの場合は原則として著作権は本人にあり、会社に帰属させるには契約書での明示が不可欠です。曖昧なまま運用すると、過去の記事について「著作権者の許諾がないまま利用している」として問題化することもあるため注意が必要です。
社内制作物における著作権の帰属については、就業規則・契約書・運用マニュアルで明確にし、スタッフにも方針を周知しておくことが、トラブルを防ぐ第一歩となります。 参考: 文化庁|著作権について
「他社記事の盗用」と主張された場合の対応と社内確認のポイント
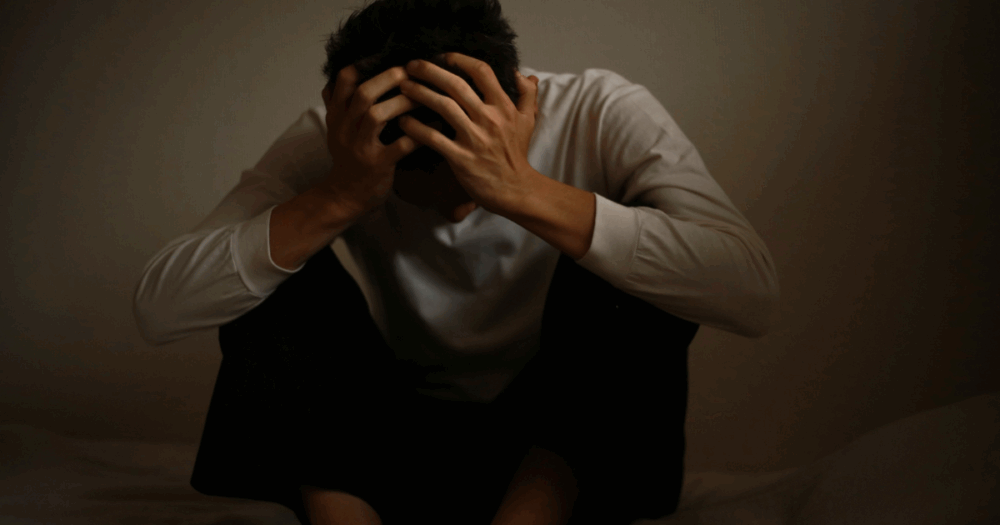
「自社のブログ記事が、他社の記事を盗用しているのではないか」と指摘された場合、まず重要なのは感情的に反応せず、事実関係を丁寧に確認することです。著作権侵害の成否は、単なる「似ている」だけではなく、その内容に創作性があるかどうか、また当該記事が依拠して作られたものかどうかといった法的な観点から判断されます。
まず確認すべきは、問題とされている記事が自社スタッフのオリジナルであるかどうかです。過去のイベント告知文やブログ記事で、外注や他のスタッフと共同で制作したものなどがある場合は、関係者から事情を丁寧に聴き取りましょう。
しかし、既に記事を削除していたり、作成経緯が不明確だったりするケースも少なくありません。そのような場合は、「当該記事が現時点で存在しないこと」「社内でも確認できないこと」を丁寧に伝え、相手方の主張を冷静に受け止める必要があります。
また、社内で記事を書く際に、他社サイトを「参考にしたつもり」で部分的にコピー&ペーストしていた…というケースも見られます。この場合、「参考」と「盗用」の境界線が非常にあいまいになりがちです。著作権法上、他者の著作物を用いるには「引用の要件(出所の明示・主従関係・改変なし)」を満たす必要があります。詳細は文化庁のガイドラインもご確認ください。トラブルが発生した際には、弁護士を通じて、事実関係と法的リスクの分析を行い、場合によっては謝罪・削除・再発防止策の提示といった損害拡大防止の対応も検討すべきです。軽視すれば、信頼失墜や訴訟リスクにもつながるため、早期対応と社内体制の整備がカギとなります。
社内で整備しておくべき「著作権のルール」とスタッフ教育の進め方

著作権トラブルを未然に防ぐためには、社内でのルール整備と教育の徹底が欠かせません。特に、ブログ記事やイベント告知、SNS投稿といった“ライトな”コンテンツほど、軽い気持ちで他社の文言や構成を参考にしてしまいがちですが、企業としての発信である以上、法的リスクを踏まえた管理が求められます。
まず基本となるのが、社内ガイドラインの整備です。以下のような事項を明文化し、誰が見てもわかる形で共有しておくことが有効です。
・他社サイトのコピー&ペーストは禁止
・引用する場合は、出典と引用範囲を明記し、文脈上「従」の扱いにすること
・外部資料を使う場合は、画像・文章ともに著作権の所在を確認すること
・外注や業務委託スタッフには、納品物の著作権譲渡の明示を徹底すること
加えて、「なぜこのルールが必要なのか」という法的背景やリスクの理解を促すことも重要です。単に禁止事項を伝えるだけでなく、過去の炎上事例や訴訟事例などを交えて説明すれば、スタッフの理解も深まります。実際に記事を執筆・公開するスタッフに対しては、実務的なワークフローの整備もセットで行いましょう。たとえば、以下のようなフローが考えられます。
・記事公開前に第三者チェック(社内または顧問弁護士)を行う
・「参考にしたサイト」がある場合は、明記して共有する
・外注記事には契約書と納品時のチェックリストをセットで運用する
なお、万が一トラブルが発生した際に備え、作成経緯や元データの保存・記録を残しておくことも推奨されます。「誰がいつ何を作成したか」が分かる体制を構築しておくことで、不当な盗用指摘への防御力も高まります。
まとめ
スタッフが作成するブログ記事やイベント告知文にも、著作権が関わる場面は少なくありません。業務中の制作物であっても、誰が権利を持ち、どう扱うべきかを明確にしておかないと、思わぬトラブルにつながることもあります。
他社から「盗用だ」と指摘された場合、感情的に反論するのではなく、事実関係の確認と法的な観点での冷静な判断が必要です。そして、トラブルを未然に防ぐためには、著作権に関するルール整備とスタッフ教育の徹底が不可欠です。
弊所では、社内ルールの策定支援やトラブル対応のご相談も承っております。ご不安な点があれば、早めにご相談いただくことをおすすめします。
【弁護士の一言】
SNSやHPの更新などによる企業広告が当たり前の世の中になり、中小企業では、自社でコンテンツ作成をすることも増えてきたと思います。そのため、今回お話しした著作権トラブルも増加した印象が強いです。
「著作権フリー」で検索しても、そこに表示されたコンテンツが「有償素材」であったなんてトラブルの相談も受けました。「著作権フリー」で確認したものが全て著作権フリーではなく、具体的なコンテンツが有償か無償かはしっかりとチェックしましょう。
