2025年06月27日
「取引先と急に連絡がつかない」「弁護士から“破産申立を受任した”との通知が届いた」「裁判所から“破産手続開始決定”の郵便が…」――。
こうした場面に直面したとき、経営者や総務担当として即座に判断しなければならないのが、「本当に破産したのか?」「債権回収は可能なのか?」という初動対応です。
実際には、「夜逃げ」「休眠」「破産」は全く別の法的状態を指しており、それぞれ対応方法も異なります。見極めを誤ると、回収のチャンスを逃したり、自社の与信管理にも影響を及ぼしかねません。
本記事では、取引先の状況をどう見極めるか、どのように対応すべきかを弁護士の視点でわかりやすく解説します。
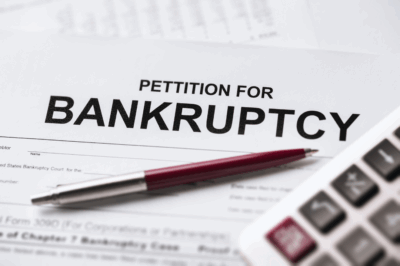
「破産」「夜逃げ」「休眠」…何が違う?初動判断の基礎知識
取引先が突然音信不通になると、「破産したのか?」「夜逃げか?」「会社を畳んだのか?」と慌てることも少なくありません。しかし、それぞれは法的にも実務上も意味が異なり、対応も変わってきます。
まず「破産」とは、裁判所が関与する正式な法的手続きです。取引先が支払い不能に陥り、裁判所に破産を申し立てた場合、通常は弁護士が代理人として「破産申立受任通知」を債権者に送付し、後日「破産手続開始決定」が裁判所から届く流れになります。これが基本的な破産処理のスタートです。例外的に、密行型と呼ばれるように、破産申立代理人弁護士が受任通知を送らずに、いきなり裁判所から破産決定通知が届く場合もあります。 一方、「夜逃げ」とは法的な用語ではなく、実務上は代表者が無断で連絡を絶ち、所在をくらます行為を指します。この場合、破産手続は始まっておらず、裁判所も弁護士も関与していないことが大半です。債権者側で登記簿や現地調査、内容証明郵便などによって現況を確認し、債権保全措置を講じる必要があります。 また「休眠会社」とは、税務署や法務局への届出により、事業活動を停止している法人を指します。形式的には「活動停止」ですが、会社法上は清算手続に入っていない限り、法人格も債務も残っています。 これらの違いを早期に見極めることが、無駄な督促や誤った債権処理を防ぎ、次の一手にスムーズに進むための鍵となります。弁護士から「受任通知」が届いたらどうする?
取引先の破産に関して、まず債権者の手元に届くのが「破産申立受任通知」という文書です。これは、弁護士が破産申立の代理人に就任したことを知らせるもので、まだ裁判所が正式に「破産手続開始決定」を出したわけではありません。 この通知が届いた時点では、破産手続は始まっていないため、相手に財産が残っている可能性があります。自社の債権状況を把握し、担保権や相殺の可否、履行済み義務の有無などを洗い出しましょう。 通知には「債権届出は破産開始後に」と記載されていることもありますが、社内では経理・法務・営業が連携して備えるべきです。また、通知元の法律事務所の信頼性を確認することも忘れずに。悪質ななりすましや詐欺の可能性もゼロではありません。冷静に内容を確認し、不明点があれば通知記載の連絡先や、顧問弁護士への確認を行うことが、余計なトラブルや誤解を防ぎます。
相手が破産した場合の債権回収とリスク管理
裁判所から「破産手続開始決定通知」が届いた場合、相手方は正式に破産手続に入り、破産管財人が選任されます。この段階でまず行うべきなのが、「債権届出」です。届出書類は、破産管財人が指定した様式と期限で提出する必要があります。
債権額の根拠となる契約書・納品書・請求書などの資料をそろえ、社内で債権内容を整理しておきましょう。届出期限に間に合わなければ、配当の対象から外れる可能性もあります。
債権者集会が開かれる場合は、回収見込みや破産者の財産状況について情報を得るチャンスです。担保権を有する場合は、別除権として優先的に回収できる場合もあります。
まとめ:見極めと初動が損失を左右する
取引先の破産や夜逃げ・休眠状態は、突然にやってきます。最も大切なのは、状況を早期に見極め、焦らず対応することです。破産の場合は、債権届出や保全措置を適切に行うことで、損失を最小限に抑えることも可能です。 「通知は届いたが、これは正式な破産なのか?」「今すぐ何をすべきか?」――そうした迷いがある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。※弊所では、企業向けに破産対応の初回相談も承っております。お気軽にご相談ください。
参考リンク(外部)
- 裁判所:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_02_02/index.html
- 法務省:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00098.html
- 中小企業庁: https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq16_tosankyosai.html
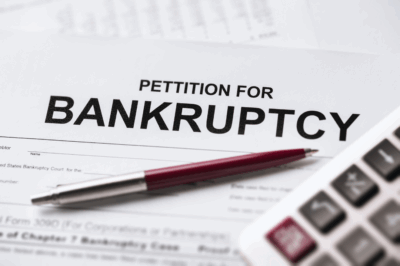
【弁護士の一言】
破産は法的に認められた正式な徳政令です。取引先企業としては残念ながら、破産手続をされてしまうと、どうしようもないことが多いです。他方、問題になりやすいのが、破産手続を正式に経ずに、夜逃げする、音信不通になるようなケースです。このような場合、倒産防止共済をはじめ、取引先破産の保険等も利用できないことが多いです。煮え切らない態度の相手には、あえて民事訴訟を提起して破産の決断をさせるなどという対応を行ったケースもあります。
いずれにせよ、初動対応はなかなか複雑な部分もあり、焦らず顧問弁護士等と相談しながら進められるとよいかと思います。
【文責:弁護士 山村 暢彦】
