2025年09月05日
「写真と違う料理が出てきた」「接客がなっていない」。飲食店を営んでいれば、一度はこうしたクレームに直面するものです。通常であれば、現場スタッフや店長が丁寧に対応し、一定のところで収束するのが一般的でしょう。
しかし中には、「社長を出せ」「本社の代表に謝罪させろ」と、1,000円にも満たない食事をきっかけに、エスカレートした要求を続ける“悪質クレーマー”も存在します。現場対応では収まらず、支店長やエリアマネージャーを超える対応を求められることも(カスタマーハラスメントについて)
こうしたケースでは、現場での対応だけでは限界があります。実際に対応した案件では、弁護士が介入することで、クレーマー行為が鎮静化した事例もありました。
本記事では、店舗現場での限界、弁護士による対応、そして店舗経営者が取るべき備えについて、実例をもとに解説します。
クレーム対応の限界:現場で対処できない「過剰要求」とは

飲食店をはじめとするサービス業では、日常的にお客様からのクレーム対応が発生します。「料理の提供が遅い」「写真と実物が違う」「スタッフの態度が悪い」といった声に対し、多くの店舗では店長や責任者が丁寧に謝罪し、返金や代替品の提供などで対応を試みます。
しかし、すべてのクレームが常識的な範囲に収まるとは限りません。実際に当事務所に寄せられた相談では、1,000円未満のランチに関して「社長を出せ」「本社の代表と話をさせろ」といった要求が繰り返され、対応が長期化しているケースがありました。
このようなケースでは、現場の店長やエリアマネージャーがいくら対応しても、相手は引かず、要求内容は次第にエスカレートしていきます。対応のたびに時間と人手が奪われ、他の顧客対応や業務に支障をきたすようになれば、もはや“お客様対応”の範疇を超えて「業務妨害」の様相を呈してきます。
こうした場合に、役員や代表取締役といった「会社の最終責任者」が安易に対応してしまうと、相手は「ここまで動かせた」と味をしめ、さらに無理な要求を重ねる危険があります。責任ある立場であるほど、表に出ることは避けなければなりません。
この段階で重要なのは、現場対応に“線引き”を設けることです。支店長や本部マネージャーまでで対応を完結させ、過剰な要求については「法的対応も視野に入れて判断する」旨を明確に伝える必要があります。
それでも対応が困難な場合には、早期に弁護士へ相談することが、店舗の平穏と従業員の安全を守るうえで重要な判断となります。
弁護士が介入した実例:堂々巡りの怒鳴り声と電話攻勢
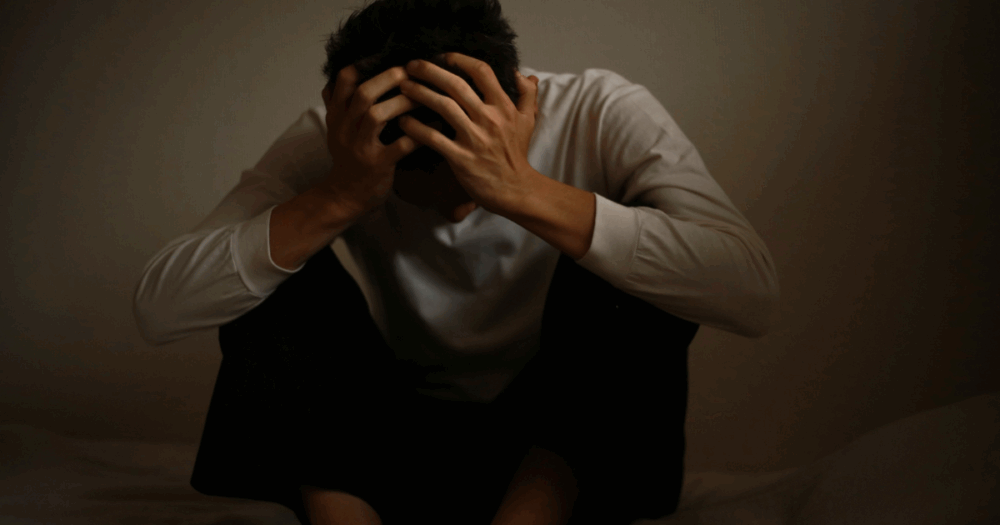
実際に対応したある飲食店のケースでは、現場スタッフによる丁寧な対応、店長からの謝罪、本部マネージャーの介入を経ても、クレーマーによる要求は止まりませんでした。
問題の発端は、「メニュー写真と違う料理が出てきた」とする不満からでしたが、次第に要求はエスカレートし、「社長を出せ」「会社のトップと話をさせろ」と、本来の飲食サービスとは関係のない内容へと発展。1,000円にも満たない代金を盾に、店舗や本部へ連日電話をかけ続け、現場は疲弊していました。
事態の沈静化を図るため、店舗側からの依頼で弁護士が介入。まずはクレームの電話窓口を当職が引き取り、以後の連絡はすべて弁護士が対応する体制に切り替えました。
ところが、相手は弁護士に対しても怒鳴り声をあげ、同じ主張を繰り返すばかり。正当な請求根拠もないまま堂々巡りの主張を続け、こちらが通話を終了すると、今度は「弁護士が対応しない」として弁護士会に苦情を申し立てる行動に出ました。
このような場合、相手が匿名であることに安心し、“言いたい放題”になっているケースが少なくありません。そこで当職は、弁護士会を通じて「弁護士会照会制度」を活用し、電話番号をもとに氏名・住所を特定。そのうえで、「これ以上の連絡は業務妨害とみなす」「法的措置も検討している」旨を正式に通知しました。
すると、それまで強気だった態度は一転。以後の連絡は途絶え、店舗への電話も止まり、問題はようやく終息しました。
匿名性を盾に過激な言動を繰り返す相手に対し、法的な“名指し”と責任を伴う対応を取ることが、最も効果的な抑止になる。それを実感させられた一件でした。
店舗経営者がとるべき対応策:現場対応と法的介入の使い分け

クレーム対応において重要なのは、「どこまで現場で対応し、どこから弁護士に委ねるか」の判断基準を明確にすることです。ほとんどの顧客対応は、店長やエリアマネージャーレベルで丁寧に対応すれば解決します。しかし、ごく一部の悪質クレーマーは、「謝罪の形」よりも「相手の立場を引きずり下ろすこと」や「無理筋の要求を通すこと」に執着しており、対応が長引くほどエスカレートしていきます。
まず店舗として行うべきは、「一定以上の立場の人間が安易に対応しない」ことです。特に、代表取締役や経営層が前面に出ると、相手に「ここまで引き出せた」という達成感を与え、次のターゲットにもなりかねません。現場から本部対応へと段階を踏みながら、最終的な交渉窓口は限定し、クレームが法的な領域に達する場合には、ためらわずに弁護士へのバトンタッチを検討しましょう。
次に、クレームの記録を「言った・言わない」にならないよう、逐一記録しておくことも重要です。日時、内容、対応者、相手の言動などを記録しておくことで、後に証拠として使えるだけでなく、エスカレート前に早期対応する判断材料にもなります。
さらに、クレームが「業務妨害」「脅迫」「名誉毀損」といった違法性を帯びてきた場合、早めに弁護士へ相談することで、事態がこじれる前に収束を図ることができます。特に電話攻勢や店舗への執拗な訪問が続く場合には、警告書の送付や発信者情報の照会、最終的には刑事告訴も視野に入れた対応が可能です。
「すべてを現場で抱え込まない」「弁護士に相談するタイミングを逃さない」これが、現代のクレーマー対応において、経営者が持つべき戦略的視点です。
まとめ
・日常的なクレームと、過剰要求を繰り返す“悪質クレーマー”は分けて対応すべきです。
・現場で対応しきれない場合、早期に弁護士を介入させることで被害の拡大を防げます。
・弁護士が「法的責任」を明示することで、沈静化に至るケースも少なくありません。
- 当事務所では、店舗経営者の皆さまの現場負担を減らすための法的対応をサポートしています。対応にお困りの際は、お気軽にご相談ください。
-
【弁護士の一言】
-
当時対応していた際の正直な感想としては、「もう俺がランチ代払うから怒るのやめろよ…」というのが、本音でした。それでも、ここまで過剰に攻撃的になって従業員や会社側への対応を求めるような方は、一種「病んで」いて、自分の憂さ晴らしをするために、店舗側に過剰に怒りをぶつけているようなケースも多いです。また、今回のように、「自分の情報が知られていない・安全な立場だ。」と考えて、激昂するような方もおり、弁護士が介入の上、正式な手続で住所等を把握すれば、一気に沈静した点も参考になります。
-
クレーマーについては、対応労力という企業側のリソースを奪われてしまうことに加えて、従業員側が過度のストレスで病む、退職してしまうなど、せっかく育てた優秀な方が辞めてしまうようなきっかけにもなりかねません。
企業としては、「カスハラ・クレーマー」対策は非常に重要な課題だと言えるでしょう。
