2025年09月02日
資金繰りが厳しい。借入金の返済に追われ、従業員の給与や税金の支払いも滞りがち。そんな状況に直面しながら、「会社を破産させるしかないのか」と一人で悩む経営者は少なくありません。特に中小企業では、社長が個人保証や私財を背負って経営を続けているケースも多く、「破産」は“人生の終わり”のように感じられるかもしれません。
しかし、会社破産はすべてを失う行為ではなく、負債の清算と再出発のための法的手段の一つです。むしろ、対応が遅れることで取引先や従業員、家族にも深刻な影響を及ぼすケースが少なくありません。
本記事では、「会社を破産させるべきかどうか」の判断ポイント、破産手続の流れ、そしてメリット・デメリットについて、企業法務に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。将来を守るために、正しい選択肢を冷静に検討しましょう。
会社破産とは?〜法的な定義と基本の流れ

「会社が破産する」とは、債務の返済ができず、法律に基づいて裁判所に申立てを行い、破産手続を通じて会社の資産を清算することを意味します。これは、単なる経営撤退とは異なり、債務整理のための法的な仕組みです。破産法に基づいて手続が進み、裁判所が「破産開始決定」を出すことで、会社の財産管理が破産管財人に移されます。
破産手続には、主に次のような流れがあります。
- 1、弁護士などを通じて裁判所に破産申立て
- 2、裁判所が破産手続開始を決定(通常は破産管財人が選任される)
- 3、資産の調査・売却・債権者への配当
- 4、債務の残額は、原則として免責(会社の場合、清算により終了)
なお、会社の破産と代表者個人の破産は別物である点にも注意が必要です。会社が破産しても、代表者が連帯保証人となっていれば、個人としての返済義務は残るため、同時に代表者個人の破産を検討するのが原則です。
「会社破産=倒産」というイメージがありますが、これはあくまで法的清算手段の一つです。むしろ、事業停止後も曖昧に放置された状態よりも、法的に整理されることで債権者にも明確な説明ができ、再出発の道筋を整える第一歩となります。
会社を破産すべきか?判断のポイント
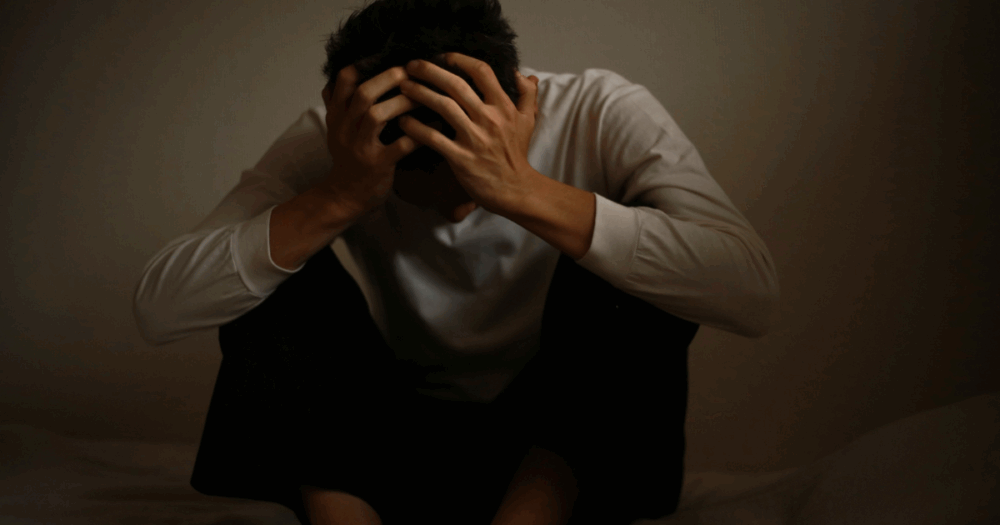
経営が苦しいからといって、すぐに「破産」を選ぶ必要はありません。重要なのは、「破産を選ぶべき段階かどうか」を冷静に見極めることです。ここで判断の材料となるのが、「支払不能」や「債務超過」といった法律上の基準です。
まず「支払不能」とは、売上や資金繰りでは、もはや当面の支払い(従業員の給与、税金、仕入代金など)が継続的にできない状態を指します。一方、「債務超過」は、資産よりも負債の額が大きくなっている状態です。このいずれかに該当すれば、破産申立てを検討する余地があるとされています。
とはいえ、会社には「破産以外の選択肢」も存在します。たとえば、金融機関とのリスケジュールである「任意整理(返済条件の見直し)」や、M&Aによる事業譲渡、場合によっては民事再生手続を活用することも可能です。これらの選択肢を比較検討せずに、早急に破産を選ぶのは避けるべきです。
実務上、以下のような兆候が重なる場合には、早めに専門家に相談すべき段階に来ているといえます。
- ・借入返済のリスケを繰り返しているが、資金繰りの改善が見込めない
- ・税金・社会保険料の滞納が常態化している
- ・経営者が個人資産から資金を投入しても資金ショートが解消しない
- ・売掛金の回収見込みが立たず、支払いが優先できない
- ・従業員への給与支払いすら危うい状況
こうした状況下で「もう少し様子を見よう」と判断を先送りすることは、かえって被害を広げる原因になりかねません。冷静な現状分析と選択肢の整理のためにも、弁護士など外部の専門家に相談することが重要です。
会社破産のメリット・デメリット

「会社を破産させる」と聞くと、多くの方が“すべてを失う”というイメージを抱きます。しかし、実際には正しく手続きを踏めば、むしろ新たなスタートに向けた一手となることもあります。ここでは、会社破産のメリットとデメリットを整理してみましょう。
◾️破産のメリット
第一に、債権者対応の負担から解放される点は大きなメリットです。破産手続が開始されると、以後の債権者とのやり取りは裁判所が選任した破産管財人が行うため、経営者自身が矢面に立つ必要はなくなります。
また、破産手続を通じて会社財産をすべて処理することで、債務を清算し「一度リセット」できることになります。経営再建や新たな事業への挑戦に向けた前向きな一歩として、早期に破産を選択するケースも少なくありません。
さらに、私的整理やずるずると事業を継続するよりも、従業員や取引先への誠実な対応につながる場合もあります。法的手続きを通じて説明責任を果たすことで、後の関係再構築がスムーズになることもあるのです。
◾️破産のデメリット
一方で、当然ながらデメリットも存在します。最大のリスクは、代表者が連帯保証人になっている場合に、会社破産と同時に個人破産を迫られる可能性がある点です。会社だけでなく、自宅や預貯金など個人資産も失う可能性があるため、慎重な判断が必要です。
また、破産手続は「官報」などで公告されるため、一定の社会的信用を失うリスクもあります。再起を目指す際には、新たな資金調達や営業活動に影響が出る場面もあるでしょう。
さらに、従業員の雇用・退職処理、取引先との契約の終了、顧客への説明など、社会的責任の整理も伴います。これらの対応を怠ると、法的トラブルや reputational damage(評判リスク)につながるおそれもあります。
まとめ:会社破産は「終わり」ではなく「選択肢」のひとつ
会社破産は、事業の失敗を意味するのではなく、将来への再出発のために必要な「法的整理の手段」です。
「支払不能」や「債務超過」の状態が続く中で、破産手続を選択することで、債務整理の道筋が見え、精神的な重圧からも解放されます。
ただし、破産には個人保証や社会的信用への影響といったデメリットもあるため、安易に判断するのは危険です。
迷ったときこそ、弁護士など第三者に相談することが重要です。早い段階での相談が、会社・家族・自身の未来を守る第一歩となります。
弊所では、会社破産だけでなく、事業再生やM&Aなど他の選択肢も含めたご相談を承っています。お気軽にご相談ください。
【弁護士の一言】
筆者自身、実際に、破産以外の選択肢で終結した事案も経験しました。債務超過、支払不能の状態で、従業員も全員解雇し、激しい債権者の督促やクレームを受けながらも、夏の暑いお盆の間に準備を行い、お盆明けに裁判所へと破産手続を決行しようとしている最中でした。
「外資系の企業が、買収してくれることになったので、破産手続をキャンセルさせてほしい。」
建設業は許認可の要件が高く、許認可要件を備えている会社でしたが負債を考慮してでも買収したいという企業が現われたのです。必死に債権者の督促の中、汗だくで書類を向き合っていた私の苦労は何だったのか…という気持ちもないわけではないですが、クライアントにとってよい解決であれば、よい結末です。
