2025年08月15日
スタートアップ企業にとって、法務は後回しになりがちな分野です。しかし、急成長を目指す企業こそ、契約トラブルや知財の取りこぼし、人事リスクなど「見えない法的リスク」に早めに備えることが欠かせません。
特に近年では、投資家や取引先も「法務体制の整備」を重視しており、しっかりとした法的支援が信用や成長スピードに直結するケースも増えています。では、スタートアップに最適な弁護士とは、どのような特徴を持ち、どんなサポートをしてくれるのでしょうか?この記事では、スタートアップが直面しやすい法務課題や、弁護士選びのポイント、顧問弁護士を活用するメリットまで、実務目線でわかりやすく解説します。
スタートアップに向いている弁護士の特徴とは

スタートアップの法務ニーズは、一般的な中小企業とは一線を画します。スピード感・専門性・伴走力が求められる中で、次のような特徴を持つ弁護士が特に頼りになります。
スピードと柔軟性:変化に即応できるパートナー
スタートアップでは、日々の意思決定が速く、事業内容も流動的です。例えば、資金調達の直前にNDAや投資契約の見直しが必要になることもあります。こうした局面で「今すぐ相談できる」「柔軟に対応してくれる」弁護士の存在は、経営判断の後押しとなります。
幅広い法務知識:一人で何役もこなせる力
資金調達、雇用契約、業務委託、知的財産、株主対応…。創業期には専任の法務部門がないため、これらを一手に担える弁護士が重宝されます。専門分野に偏らず、実務に即したアドバイスができる「ジェネラリスト型の法務」が理想です。
経営視点と業界理解:ただの「法の番人」では足りない
単にリスクを指摘するだけでは、スタートアップの現場には響きません。プロダクトのスケールや業界のトレンドを理解し、「どこで攻め、どこで守るか」を一緒に考えてくれる弁護士こそが、経営者にとっての“右腕”となります。
加えて、難しい法律用語を噛み砕いて説明できるコミュニケーション力や、起業家・投資家とのネットワークを持つ人材であれば、さらなる成長の後押しとなるでしょう。
スタートアップが押さえるべき契約・法務の基本
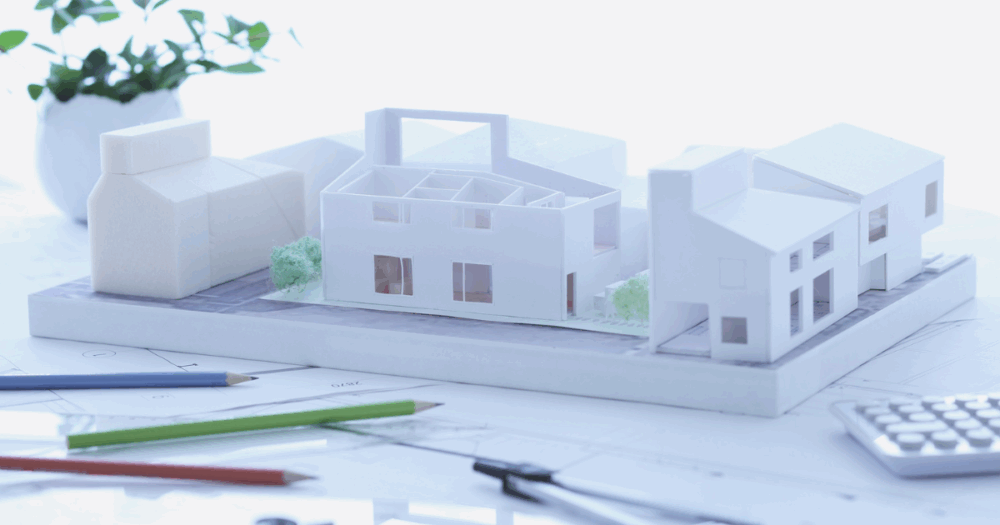
「とりあえず口頭で合意した」「知り合いの雛形を使い回している」――スタートアップでは、スピード重視のあまり、契約書の整備が後回しにされがちです。しかし、法務を軽視した結果、後に大きなトラブルに発展するケースも少なくありません。以下のポイントは、どのフェーズの企業であっても必ず押さえておくべき基本です。
契約書の作成・レビューは必須
すべての取引には、書面の契約書を交わすべきです。特に業務委託・共同開発・出資・株式譲渡などでは、「口約束」はリスクそのもの。弁護士によるレビューを通じて、権利関係や損害賠償リスクを明確にしておくことで、トラブル回避につながります。
雇用・外注契約、知財の取り決めも重要
創業メンバーとの関係性に甘えがちですが、「誰がどんな権利を持っているか」を明確にしないと、後から揉める原因になります。雇用契約・業務委託契約では、労働条件や業務範囲、秘密保持・競業避止義務まで明記しておくことが大切です。
また、プロダクト開発に関与した外部のエンジニアが著作権を主張してくるケースもあるため、知的財産の帰属は最初から契約で明確にしておきましょう。
契約の「背景」と「出口」にも目を向ける
契約書は単なる形式ではなく、「なぜその取引をするのか」という目的や、「終了や紛争が起きたときどうするか」といった出口戦略まで視野に入れて設計する必要があります。解除条件、準拠法、管轄裁判所なども、初期段階で詰めておくことで、万が一の際にも冷静に対応できます。
弁護士がスタートアップにもたらす具体的な価値

「弁護士=トラブルが起きたときに相談する人」と思っていませんか?実際には、スタートアップの成長フェーズにおいてこそ、弁護士は戦略的なパートナーとして活躍します。単なる法的な“守り”ではなく、“攻め”にも強い弁護士を活用することで、次のような価値が得られます。
新規事業や資金調達の加速支援
例えば、新しいビジネスモデルが法律上問題ないかを事前に確認できれば、経営判断のスピードが格段に上がります。また、エンジェル投資やVCとの投資契約も、弁護士の支援があれば交渉が有利に進み、出資条件のリスクを最小限に抑えることができます。
知財・人事まわりのトラブル予防
技術やノウハウの漏洩を防ぐ知的財産の保護、労務トラブルを未然に防ぐ雇用契約・人事制度の整備なども、初期から弁護士が関与することでリスクを最小限にできます。特に人の出入りが激しいスタートアップでは、ここを見落とすと命取りになりかねません。
信頼とブランドの形成に直結する「法務体制」
投資家や大手企業との取引では、「法務の体制が整っているか」が重要な評価ポイントになります。顧問弁護士が日常的に関与していれば、外部からの信頼度が上がり、資金調達や提携のチャンスも広がります。
加えて、法務部を社内に持たずとも、外部の弁護士をうまく活用することで、高い専門性を低コストで確保できる点も見逃せません。
スタートアップこそ「攻めの法務」で成長を加速させる
スタートアップの成長には、スピードと挑戦が欠かせません。
だからこそ、法務の整備を「守り」として後回しにするのではなく、「攻め」の成長戦略の一部として捉える視点が重要です。本記事では、スタートアップに向いている弁護士の特徴から、契約・法務の基本、そして弁護士を活用することで得られる具体的な価値までを実務目線で整理してきました。
「自社に合う弁護士がわからない」「契約書をチェックしてほしい」「顧問契約を検討している」そうしたお悩みがある方は、ぜひ初回無料相談をご利用ください。顧問契約検討の場合には、初回無料相談にて対応しております。スタートアップの事業フェーズや課題に応じて、法務の整備や顧問契約の進め方をご提案いたします。
【弁護士の一言】
「スタートアップなので、まだ顧問弁護士なんて…」という感覚の方がまだ多いのかもしれません。ですが、近年は法的コンプライアンスが非常に重要となり、現代の若い経営者層では、税理士・社労士に並び、企業運営には顧問弁護士が必須だと、設立後間もない状況から顧問弁護士の依頼をされる企業も多いです。 実際に弊所でも、新規設立後比較的間もない、建設業社、オフィス機器販売業者、リフォーム業者、アパレル事業者などの顧問弁護士対応をしてきた経験もあります。スタートアップ時の方が、取引先企業から強い要望をぶつけられるようなケースもあり、法務が必要になるような局面も多いです。弊所では、スタートアップ企業用の特別費用プランも設けておりますので、気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
